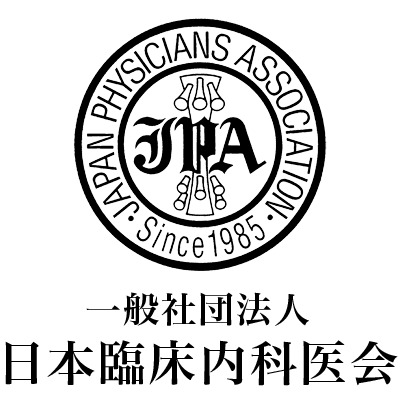会誌の紹介 backup

第24巻5号
高齢化と日臨内 日本臨床内科医会 副会長 望月紘一
平成22年の新年が明け、21世紀は早くも二度目の10年が始まることとなる。私が東京の住宅地域で診療所を開設して30年が経過した。開業当初は30歳台であった私も今や高齢者といわれる年齢になり、通院している患者さんたちも当然変化してきている。近くの大きな団地の平均的家族の家長の年齢層も、40~50歳台から70~80歳台へと変化した。社保本人・家族が2/3、国保1/3であった患者層も、社保1/3、国保1/3、残りの1/3は75歳以上の後期高齢者となった。毎月通院している高齢の方々も次第に足腰が弱まり、80歳も後半を過ぎると通院すること自体が体力的に困難となることが少なくなく、通えなくなった時にはどうすればよいか質問され、「その時は、私が定期的に往診して対応します」などと即答できなくて困惑する。高齢化社会が到来 したことはずいぶん前からいわれていたが、自分が高齢となり自院の患者さんも高齢となってはじめて強く実感される。通院患者への対応に手いっぱいの現状と、これから低下してゆくであろう自分の体力を考えてしまうが、今後、在宅医療を重視した診療体制への方向転換の必要性も感ずる。
さて一方で、日臨内の会員の年齢構成は如何であろうか。各県内科医会の集合体である日臨内では、全会員の年齢の詳細を把握することはむずかしいが、認定医制度、専門医制度に加入している会員のデータでは、70歳台は当然として、80歳台、90歳台の先生方も少なくなく、高齢会員が多いことが特徴である.若い会員の新規入会がなかなか進まない悩みはいつも問題となり、その対策は喫緊の課題であることはもちろんであるが、視点を変えて高齢会員が多い現状を踏まえた対策も必要である。
高齢の患者にとってみれば、高齢者の体調や心理が理解できる年齢であつて、なおかつ医学の進歩に取りされずに新しい医学知識を備えた医師からの診察を受けたいと思っていると考えられる。家庭環境の違い、加齢現象のあらわれ方、生活習慣の影などが個人個人で大きな差となることが高齢者の特徴であり、それを理解できるのは、その地で永年地域医療に従事した医師であろう。そのような経験豊富な高齢会員が多いことも、正に日臨内の大きな誇りの一つである。
創立25周年を迎える日臨内では、まず会員自身がみずからの健康を保持・増進していくために役立つ事業を展開し、そのうえで高齢化日本に貢献する医師となるために役立つ活動が求められる。そこで、日臨内では近い将来、会員の健康調査が予定され、また今後ますます重要となるであろう在宅医療について、その基本から検討する事業を計画中である。会員の先生がたのご協力をお願いしたい。